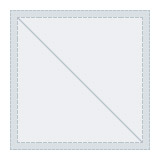ポーランドの人
物語に登場する「女」は、バルセロナの音楽サロンを運営する委員会のメンバーであるベアトリス。「男」は、ショパン弾きで名を馳せ、サロンに招聘されたポーランド人の老ピアニスト、ヴィトルトだ。ショパンの「前奏曲」を弾く彼は、ダンテの信奉者でもある。ヴィトルトはベアトリスに一目惚れして、ポーランドに帰国した後も、彼女にCDや恋文を送り続ける。よき夫がいて息子は成人し、孫もいる49歳のベアトリスは、ショパン弾きのヴィトルトの求愛をばかげていると思いつつ、その言葉や、音楽、自分への好意の示し方に興味津々に反応するうち、マヨルカ島の別荘にヴィトルトを招くことになるが……。
80代になったクッツェーが、ベアトリスの視点から求愛される心理を細やかに分析的に描き出そうとする。
「これはヨーロッパの古典としてのダンテとベアトリーチェの神話的恋物語を、パスティーシュとして再創造する頌歌(オード)なのか。それとも、長きにわたりロマン主義の底を流れてきた“恋愛をめぐる男と女の感情と心理” を、現代的な視点から徹底分析した挽歌(エレジー)なのか。」――訳者あとがきより
すれ違う男と女。ダンテにとってのベアトリーチェがヴィトルトの思い描く究極の「恋人」らしく、これまでの〈世界文学〉に登場した「恋愛」が、いかに男性側からの一方的な妄想に基づいたものであったかに光が当てられ、クッツェーらしい皮肉を効かせながらコミカルに描かれる。
言語が大きなテーマになっているのも見逃せない。二人が意思疎通で使うのは英語だが、ポーランド語が母語のヴィトルトは英語を流暢に話せない。彼は死を前にしてダンテのベアトリーチェへの憧憬を模倣し、ポーランド語で詩を書き残す。その詩をベアトリスは翻訳者に頼んでスペイン語に翻訳しないと読めない。全篇にスペイン語、ポーランド語、ロシア語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、ラテン語などが散りばめられるが、英語は距離をもって扱われる。ヨーロッパ大陸の歴史と言語をめぐる微妙な関係をも考えさせられる。
本作はクッツェーの第一言語である英語で書かれた作品だが、英語文化の覇権性に抗うクッツェーは、まず昨年7月にカスティーリャ語版を刊行し、今年3月にオランダ語版を刊行、5月にドイツ語版、カタルーニャ語版、日本語版(本書)が刊行される。そのあと、7月に英語版が刊行される予定。
- この本が読めるところ
- 借りた人・借りている人
- 貸出OK
- じゃじゃの私設図書館