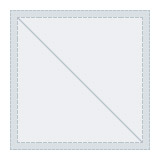異国の窓から
取材先のウィーンのオペラハウスで、著者はいかめしい顔の係員にまくしたてる。「天井桟敷でも客は客やぞ。天井桟敷の隅で、汚い服を着てるやつのほうが、ボックス席の金持連中よりも、はるかに深い心でオペラを観るかもしれんやないか」大阪弁「必殺日本語突き」に、金ボタンの制服を着た係員もすごすごと退散する…。別れの悲しみは胸に仕舞い、素晴しい人々との出会い、出会い、出会い。綴られた、ドナウ河の美しき情景に展開する生の歓喜と悲しみ、それはもう、ファンタスティック。ヨーロッパ7カ国、そして中国を巡る笑いと涙に充ちた名紀行文。
- この本が読めるところ
- 借りた人・借りている人
- 貸出OK
- 多賀文庫
- 貸出OK
- おんせん図書館みかん(旧:山代コドン)
- まだ借りた人はいません
- 貸出OK
- もぐらのほんだな
- まだ借りた人はいません
- 貸出OK
- まちライブラリー 道草
- まだ借りた人はいません
- 貸出OK
- ふなばし駅前図書館Chiba Funabashi-shi
- まだ借りた人はいません
- 貸出OK
- ホクサンメモリアル図書館
- まだ借りた人はいません
この本を寄贈した人
八田聡美
もぐらのほんだな