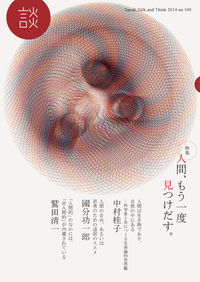
- Author中村桂子/著 國分功一郎/KOKUBUN Kouichir 鷲田清一/WASHIDA Kiyokazu
- Publisher公益財団法人たばこ総合研究センター
- ISBN9784880653433
- Publish Date2014年7月
談 no.100
デカルトを嚆矢とする機械論的世界観の登場は、人間を機械と見做し、世界を動かす物理的なシステムの構成要素、いわば歯車に還元した。歯車と最も遠くにあると思われていた人間が、歯車そのものになってしまったのである。歯車でありかつ歯車でないもの。近代以降、現代に至るまで、人間は、この相容れない両輪の、いわば「また裂き状態」に置かれ続けている。
このまた裂き状態のなかで、われわれに対し「新たな人間」という概念を模索する必要性を問うたのが、2011年3月11日に発生した東日本大震災であった。地震・津波・原発事故が、われわれに突きつけたものは、機械としての歯車から、自然である歯車への構造転換だ。今こそまた裂き状態からの脱却が求められているのだ。
3.11から3年、未だ被災地の復興は道半ばであるが、すでにあの時の記憶は風化し始めている。それとともに、3.11が投げかけた「新たな人間」という問いかけも風化し始めているのではないか。だからこそ、もう一度、3.11が突きつけた問題、すなわち「人間」そのものを、自然と科学との関係から問い直さねばならない。 弊誌は今号で、100号を迎える。この記念すべき号で、人間再考の第一歩としたい。
人間は生き物であり、自然の中にある……科学者と共につくる生命論的世界観 ・中村桂子(JT生命誌研究館館長) 科学技術が自然と向き合っていない。東日本大震災で明らかになったのは、この事実であり、現代の科学文明が抱える問題は、おしなべてこの事実に集約できるだろう。科学が生まれ、そこから開発された科学技術によって進歩を続けてきた近代。16,17世紀の科学革命を経て、自然を一種の「機械」と見なす機械論的世界観が近代を形付けてきた。機械論の特徴は、一切を数値化するところにある。徹底した数値化は、自然を操作可能な対象へと変えてしまった。要するに、自然を「死物化」したのである。私たちは、今一度自然と向き合い、自然を生き返らせることだ。それは、近代の機械論的世界観から生命論的世界観への転換を意味する。 人間が生きものであり、自然の中にあると考える立ち位置を決め、そこに足場を置き、科学がつくってきた世界観を科学者の立場から問い直すこと。東日本大震災後の人間観について、主に科学と人間のかかわりから考察する。
人間の自由、あるいは思考のための退屈のススメ ・國分功一郎(高崎経済大学経済学部准教授) 國分氏は、著書『暇と退屈の倫理学』で、「退屈と気晴らしが入り交じった生、退屈さもそれなりにあるが、楽しさもそれなりにある生、それが人間らしい生」だと言う。そして、楽しむことは思考することにつながると断言する。楽しむことも思考することも、どちらも受け取ることにおいて同じであり、人は楽しみを知っている時、思考に対して開かれているというのだ。 退屈とどう向き合っていくかという問いは、あくまでも自分にかかわる問いであると國分氏は言う。しかし、退屈と向き合う生を生きていけるようになった人間は、おそらく、自分ではなく、他者にかかわる事柄を思考することができるようになる。だとすれば、3.11以降、われわれが求めている「人と人とのつながり」を、どう解釈できるのか。それは〈暇と退屈の倫理学〉の中であげられた、「どうすれば、皆が暇になれるのか、皆に暇を許す社会が訪れるか」という次なる課題と、どう関連していくのか。暇・退屈・楽しみを切り口に、3.11以後のエシックス(倫理学)を開陳する。
「人間的」のなかには、「非人間的」が内蔵されている ・鷲田清一(大谷大学教授、仙台メディアテーク館長) ヒューマニズム、あるいは人間主義。それは、「人間」というものに、他の何とも替えることのできない固有の「尊厳」を見出す思想である。ひとがどのような境遇にあろうとも、すなわち、どのような階層に属し、どのような国籍、性別をもち、どのような年齢にあろうとも、それら一切とかかわりなく「人間」としてその存在が尊重されねばならないとする思想である。「人権」という観念もここに由来する。しかし、この「人間的」(human)という審級は、どこにその根拠をもつのだろうか。 「人間的」という言葉を措くことで、人間は、何を伝えようとしてきたのか。そして、3.11以前と以後とで、「人間的」という概念に、意味の異同が生じてはいないか。「人間的」という言葉を批判的に検討することで、3.11以後の新しい「人間」像に迫る。 ※所属などは本書刊行時のものです。
- This book can be read at
- Borrowed People
- Borrowable
- つんどく
- No borrowed yet