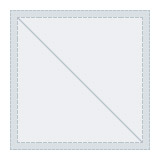土に贖う
大藪春彦賞受賞第一作!
明治時代の札幌で蚕が桑を食べる音を子守唄に育った少女が見つめる父の姿。「未来なんて全て鉈で刻んでしまえればいいのに」(「蛹の家」)
昭和初期、北見ではハッカ栽培が盛んだった。リツ子の夫は出征したまま帰らぬ人となり、日本産ハッカも衰退していく。「全く無くなるわけでない。形を変えて、また生きられる」(「翠に蔓延る」)
昭和三十五年、江別市。装鉄屋の父を持つ雄一は、自身の通う小学校の畑が馬によって耕される様子を固唾を飲んで見つめていた。木が折れるような不吉な音を立てて、馬が倒れ、もがき、死んでいくまでをも。「俺ら人間はみな阿呆です。馬ばかりが偉えんです」(「うまねむる」)
昭和26年、最年少の頭目である吉正が担当している組員のひとり、渡が急死した。「人の旦那、殺してといてこれか」(「土に贖う」)など北海道を舞台に描かれた全7編。
これは今なお続く、産業への悼みだ――。
カバー画:久野志乃「新種の森の博物誌」
【著者略歴】
河崎秋子(かわさき・あきこ)
1979年北海道別海町生まれ。2012年「東陬遺事」で北海道新聞文学賞を受賞。『颶風の王』で2014年に三浦綾子文学賞、2016年にJRA賞馬事文化賞を受賞。2019年『肉弾』で大藪春彦賞を受賞。
- This book can be read at
- Borrowed People
- Borrowable
- 土蔵屋
- No borrowed yet
- Borrowable
- まちライブラリー@ちとせ
Presented by
 10070000765
10070000765
まちライブラリー@ちとせ